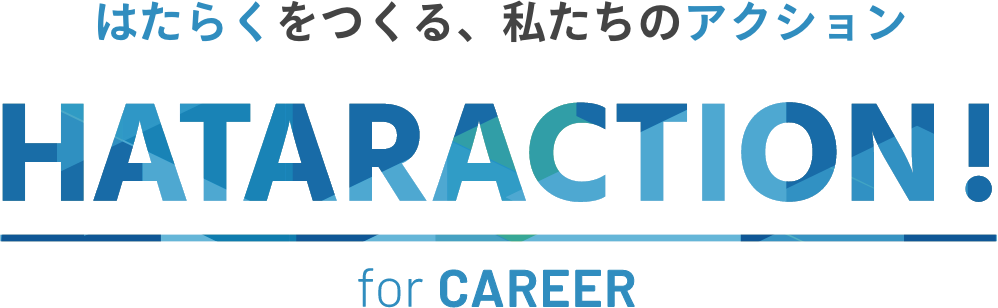社員インタビュー
2025.08.06
“楽しくはたらく”をあきらめない。仲間の未来をつくるエンジニアの挑戦
クライアントプロダクト本部 テクノロジー統括部 プロダクト横断開発部 サブマネジャー
窪田 真菜 (くぼた まな)
「エンジニアが楽しくはたらける環境をつくりたい」。そんな思いを胸に、パーソルキャリアへ転職した窪田 真菜さん。将来への不安からキャリアをスタートし、組織や仕組みを“変えていく側”へと歩みを進めた軌跡と、エンジニアとしてはたらくことの魅力について詳しく聞きました。
将来への不安から地元にない選択肢を。“技術”という扉を開いたエンジニアの道
エンジニアになろうと思ったのは、高校時代の授業がきっかけでした。COBOL(事務処理用に開発されたプログラミング言語 )に少し触れたところ、不思議と楽しくて、周りが苦戦する中でも自分にはスッと理解できる感覚があったんです。日々の課題やスケジュールも、Excelでマクロを組んで管理していて、自学自習で知識を身につけられたことも後押しになりました。
一方で、当時は「結婚して家庭を持つ人生」はあまり想像できず、将来に対する漠然とした不安がありました。私は地方の出身ですが、地元の事務職では生活できるだけの収入を得るのは難しく、将来への選択肢が限られていると感じていたんです。そのため、「手に職をつけたい」という思いが強くなり、新卒で派遣エンジニアとして小さな会社に入社しました。
配属された現場では「これつくってみて」と言われるまま、ゼロから簡単なシステムを組むところからのスタートでした。最初に任された仕事がうまくできたことで自信が生まれ、そこからは夢中で学び続けたんです。ただ、エンジニアとして技術を突き詰めていきたいと思いながらも、その先にどんな未来があるのかまでは見えていませんでした。
その後、1年ほどして、より実践的なスキルを身につけるため、受託開発の会社へ転職しました。しかし、そこでは過酷な案件も多く、優秀な仲間たちが疲弊し、次々に離れていくのを目の当たりにしたんです。その光景があまりに悲しくて、そうした人を救いたいと思い、チームを持つ立場をめざすようになりました。

私が本当につくりたかったのは、仕組みではなく“はたらく喜び”だった
自分の手で、仲間が前向きにはたらける環境をつくりたい――。受託開発の現場で苦しむ仲間たちの姿を見たことで、そんな思いが自分の中に根付いていきました。楽しくはたらけるエンジニアが増えれば、より良いサービスが生まれ、結果としてユーザーに価値が届いていく。その循環を支えることこそ、自分の役目なのだと考えるようになりました。
しかし、当時の職場はトップダウン色が強く、個人の裁量がまったくない環境だったんです。今の自分の力では現状を変えるのは難しいと感じ、技術と経験を深めるために、再び派遣エンジニアというはたらき方を選びました。その後、さまざまな現場を経験する中で、フォロー体制がしっかりと整った環境に惹かれ、パーソルテクノロジースタッフ(現:パーソルクロステクノロジー)に関わるようになりました。
同時に、業務の自動化にも力を入れ、エンジニアの負担を減らすことで、はたらく環境そのものをより良くしていく取り組みも進めていました。そうした中で、仲間がいきいきと楽しそうにはたらく姿を見て、「ああ、つくってよかった」と心から思えたんです。その瞬間こそが、自分にとって何よりの喜びなのだと実感しました。
とはいえ、何を「楽しい」と感じるかは人それぞれ違います。だからこそ、「一人ひとりが自分らしく楽しめる環境や機会を届けられる仕事をしたい」と、自然と考えるようになっていきました。
そうした経験を重ね、派遣エンジニアとしてやり切ったという感覚を持てたタイミングで、縁あってパーソルキャリアの方と会う機会がありました。そこで私が「エンジニアが楽しくはたらける環境をつくりたい。そのためにリーダー職に挑戦したい」と、率直に思いを伝えたところ、「それなら、やってみたら?」と迷いなく背中を押してくれたんです。
その言葉に、任せてもらえることへの信頼と挑戦を賞賛する文化を感じ、「ここなら本気で挑戦できそうだ」と思い、パーソルキャリアへ転籍しました。自分に向いているかどうかも分からない中での挑戦でしたが、「やってみたい」という気持ちを信じて、一歩を踏み出したんです。
実際に、入社してから2〜3ヶ月後には継続開発のリーダーを任され、「しっかりと機会をくれる会社なんだ」と実感しました。この経験があったからこそ、「自分の意志で挑戦していく姿勢」を、今も持ち続けていられるのだと思います。

パーソルキャリアで出会った、ユーザーの声を聞き、価値を届けるエンジニアリング
パーソルキャリアに入社してまず驚いたのは、エンジニアという立場でありながらも「事業目線を持つこと」を求められたことです。施策や企画が絶対ではないことを前提に、システムをブラッシュアップしていく姿を見て、その必要性を理解し、楽しさも感じるようになっていきました。
以前の職場では、システムをリリースしたら終わりということが多く、効果があったのかどうかも分からない状況がほとんどでした。しかしパーソルキャリアでは、プロダクトを通じてユーザーの声がダイレクトに届く環境が整っており、自分がつくった機能が使われている実感や、成果につながっている手応えを日々感じることができます。
私がもっとも避けたいのは、「使われない機能」をつくってしまうことです。だからこそ、ユーザーの反応を見ながら価値検証できる環境に、とても大きな魅力を感じています。
現在は、サブマネジャーとして、企業の採用活動を支援する法人向けシステム「CONNECT」の継続開発を担っています。求人原稿の掲載に必要な書類の承認や、応募情報の管理なども含め、候補者が応募してから内定に至るまでのプロセスを、効率的に管理できる仕組みづくりをしています。
このプロダクトに関わった当初は、十分に活用されているとは言えない状態でしたが、4〜5年かけて基盤を整備し、ようやく「ここからどんな価値を生み出せるか」というフェーズに入ってきました。企業が本当に求めているのは「選考を実施すること」ではなく、「採用を成功させること」です。
そのため現在は、エンジニア、企画、デザイナーが職種の垣根を越えて連携しながら、全員が同じ目線でプロダクトとユーザーに向き合っています。単なる業務の効率化ではなく、「選考フローの中で、いかに内定率を高められるか」という部分に重点を置き、改善を進めています。

「はたらいて、笑おう。」をエンジニアとして体現する――成長を支える文化と思い
パーソルキャリアの大きな魅力は、組織全体で成長を共有する文化があり、エンジニアとしての挑戦を後押ししてくれることです。直属の上司に限らず、エンジニアや企画、コンサルタントなど、さまざまな職種のメンバーと1on1で対話する機会があり、多角的な視点からフィードバックを受けられます。それは単なる評価ではなく、一緒に成長していきたいという意志の表れだと思っています。
自分の強みや課題を客観的に知ることで、「なぜ成長できたのか」「どうすれば再現できるのか」が明確になり、自分の成長も実感できるようになるんです。そうした気づきを他のメンバーと共有することで、相互成長にもつながっていくと考えています。
私がエンジニアの成長を実感するのは、「主語の変化」です。例えば、最初は目の前の「機能」に注目していた人が、やがて「システム全体」や「チームのあり方」まで意識した話し方になる。そんな変化こそ、成長の証だと思っています。
こうした変化を促すには、まず「与えられた要件は正しい」という思い込みから一歩離れ、自分の頭で考えることが大切です。自分の「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(なすべきこと)」を言語化し、自分で考え、行動できる人にとって、パーソルキャリアは最適な環境だと思います。
グループが掲げる「はたらいて、笑おう。」を、みんなで体現しようとしているパーソルキャリアが、私はとても好きです。私自身、メンバーが成長していく姿を見るのは本当に嬉しいですし、システムに新たな価値を加えていく過程にも、大きなやりがいを感じています。
ただ、以前は自分でなんでも手を動かしてしまい、後任の育成やチーム体制の強化が遅れてしまうこともありました。だからこそ今は、業務を少しずつチームに引き継ぎながら、属人性を減らし、私がいなくても成長が加速していくような環境づくりに取り組んでいます。
そしてこれからは、私なりのエンジニアという職種の捉え方も広めたいと考えています。エンジニアは「つくる人」だと思われがちですが、あくまでも技術は価値を届けるためのひとつの手段でしかありません。技術を磨くことももちろん大切ですが、それ以上に「誰のどんな課題をどう解決するか」を考え抜くことが重要だと思うんです。だからこそ、技術だけにとらわれない考え方を伝えていきたい――やっぱり、エンジニアは楽しいですからね。
- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。
- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。
監修者:HATARACTION!編集部
"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。







 応募ガイド
応募ガイド