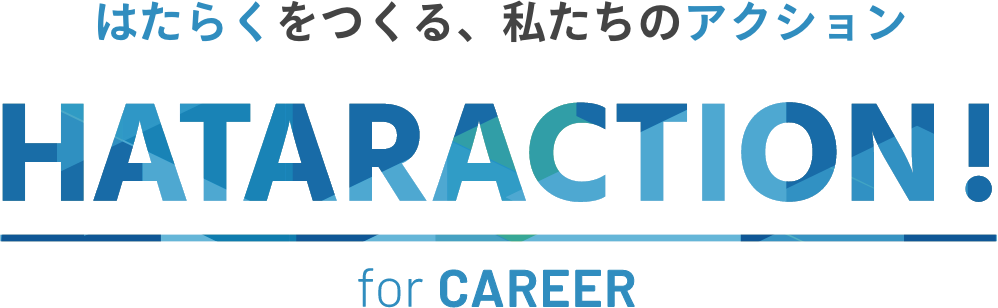社員インタビュー
2025.08.29
AIマッチングで未来を描く――100億円規模の刷新を支えるエンジニアの成長戦略
データ・AIソリューション本部 データソリューション統括部 データサイエンス部 マネジャー
吉田 雅俊 (よしだ まさとし)
SIerでキャリアの礎をきずき、現場で磨いた技術と推進力を強みにプロジェクトマネジメントを担ってきた吉田 雅俊さん。パーソルキャリア入社後は、100億円規模のプロダクト刷新と業務プロセス改善をけん引し、AI領域における新たな可能性を切り拓いています。取り組みを通じてもたらした事業と組織の変化、そしてその先に描く自身のキャリアのあり方について話を聞きました。
SIerから事業会社へ。“つくるだけ”ではない手応えを求めて踏み出した転職
大学では経営工学を専攻し、品質管理や工程の最適化、統計学、プログラミングなどを幅広く学びました。ITやデータは、「あくまでビジネスを成長させるための手段である」という視点は、今の仕事観にもつながっています。ビジネス・データサイエンス・テクノロジーという、いわゆる“データサイエンティストの三要素”に、早い段階から触れてきました。
卒業後はSIerに就職し、要件定義や設計、コーディングなど、エンジニアとしての基礎をきずきました。中でも印象深かったのは、通信キャリアのバックエンド構築プロジェクトに携わった経験です。社会インフラを担う大規模案件にプロジェクトリーダーとして参画し、100人月規模のプロジェクトを半年で完遂しました。
30代に入ってからは、常駐先の事業会社で機械学習やレコメンドエンジンの構築といった、データを扱う領域へシフトしていきました。初めて企画や営業など、異なる職種の人たちと一緒にはたらく環境に変わり、「仕事の見え方がこんなにも広がるのか」と衝撃を受けたのを覚えています。
この頃から、「データが、どのようにビジネス価値を生むのか」を意識するようになり、30代後半には、データサイエンスのモデリングやアナリティクスなど、より上流の技術領域にも踏み込んでいきました。
ただ、クライアントワークを続ける中で、「成果を出しても、自社が変わるわけではない」といった、もどかしさも感じるようになったんです。「自社の事業成長に直接貢献する環境ではたらきたい」という思いが、転職を決意する大きなきっかけとなりました。
とはいえ、当初は転職の進め方も分からず、いろいろな企業に応募しては、うまくいかない日々が続きました。そんな時、データ活用領域に精通したエージェントと出会い、HR領域に関わっていた経験を踏まえて、「パーソルキャリアであれば、きっと高く評価してもらえるはずです」と背中を押してもらえたんです。
そうして受けた面接では、偶然にも以前一緒にはたらいた方が面接官を務めていて、とても驚きました。その後、その方に社風やはたらき方についても話を聞く機会があり、「これまでの経験を活かしながら、新しいスキルを磨いていける」と確信し、2022年にパーソルキャリアへ入社しました。

100億円規模のプロダクト刷新に挑む3年計画。「自分の代名詞」をつくる覚悟
パーソルキャリアに入社して任された最初の大きな仕事は、「データ組織の業務プロセス全体の改善」と「セカンドマッチ(新着求人を自動でマッチング・紹介する機能)の刷新」という、二つのミッションです。
当時のデータ組織は若手メンバーが中心だったこともあり、情報感度は高いものの、長期運用に不安のあるコードや構成が散見されていました。そこで、SIer時代に培った経験を活かし、中長期を見据えた開発スタイルや、基本に忠実なエンジニアリングの考え方を、丁寧にチームへ浸透させていきました。
一方で、プロジェクトマネジャーとして刷新を任された「セカンドマッチ」は、約10年前に誕生した自動求人紹介の仕組みです。検索条件への依存や、検索対象の制限といった構造的な課題に加え、長年の改修によって機能が複雑化し、保守も困難な状態に陥っていました。
当時のパーソルキャリアで「セカンドマッチ」は年間100億円の売上を生む、まさに「事業の柱」ともいえる存在でした。このプロジェクトが成功すれば「自分の代名詞になる」と確信し、3年計画を立てました。
1年目はシステムの全面刷新、2年目は精度の改善、そして3年目には紹介体験の最適化。最終的には、売上を300億円規模に伸ばすという目標を独自に掲げ、「この挑戦で結果を出し、3年後の社内アワードの舞台に立つ」と決意しました。
「セカンドマッチ」は、ビジネスの根幹を支えるシステムであり、決して失敗が許されない領域です。だからこそ、HR領域へのビジネス理解、データ活用、テクノロジー知識といった3つの視点を持ってプロジェクトを推進できるのは「社内で自分しかいない」――そう奮い立たせて、この挑戦にのぞみました。

1.5倍の成果を出しても、まだ通過点。成功の先を見据えた仕組みづくり
セカンドマッチの刷新プロジェクトは、2023年1月にスタートしました。着手にあたり、まず営業職の業務実態について事業部門へのヒアリングを実施したところ、日々の業務に大きな負担がかかっている実態が浮かび上がってきました。というのも、当時の転職希望者への求人配信は、営業が入力する検索条件に依存し、毎日のように手作業で対応していたんです。本来、営業職がもっとも時間を割くべき「人と向き合う業務」が、システムの制約によって削られていました。
さらに、アクティブな候補者が約10万人いる中で、1週間以内に求人を届けられていたのは、およそ7万人。公開中求人のうち候補者に紹介された求人は、同じ期間内で全体の3分の1にも満たない配信状況でした。この構造は、絶対に解決しなければならないと強く感じました。
もちろん、開発工程の道のりは平坦ではありません。想定より「AIの精度が上がらない」「処理時間が長い」など、多くの技術的な課題が立ちはだかります。それでも、これまでの経験を活かしながら、チーム一丸となって改善を重ねていきました。
そして、2023年3月に予定通りフィジビリティ(実現可能性の評価)を実施したところ、障がいも発生せず、従来の仕組みと比較して、決定数は1.5倍に増加するという確かな成果が得られました。
この時は、「計画通りにやり切れた」という手応えと、「本当にここまで実現できたんだ」という驚きが、半分ずつ混ざった感覚でしたね。ただ、達成の喜びと同時に、すぐに浮かんだのは、ここで終わってはいけないという思いです。
実は、1年目の開発と並行して、継続的にマーケットの反応をモニタリングし、状況の変化を即座に検知・改善できるよう、モニタリングからエンハンスまでを効率的に実行できる基盤を同時に構築していました。
2年目には、リリース後のAIモデルの精度劣化をいかに早く検知し、改善サイクルを回していくかという仕組みづくりに注力したんです。約30個の改善アイデアをリストアップし、メンバーがそれぞれ担当を持って毎月のようにテストを実施しながら、AIの精度向上に取り組みました。
2025年4月にマネジメントの立場に移りましたが、これまでの取り組みが社内で評価され、目標としていた全社アワードの場にも立つことができました。本当に嬉しかったですね。
パーソルキャリアに転職する際、「自分が一生を終える時、大きな挑戦をした」と言えるようなことを成し遂げたいという、強い思いもありました。そのうえで、大きな仕事を任せてもらえたからには、できることは全力で取り組もうと決めて進んできたからこそ、今回の結果につながったと感じています。

人の心に残る仕事を技術で実現する。AIマッチングが切り拓くその先へ
パーソルキャリアの魅力の中でも、私が特に実感しているのは、「自ら手を挙げて、さまざまな挑戦に取り組めること」です。ボトムアップの文化が根付いており、スピーディーに物事を進められます。変化が激しく、技術の進化も速いサイエンス/テクノロジーにおいて、この柔軟さは大きな武器です。
さらに、部門や職種の垣根を越えた連携が取りやすく、周囲を巻き込みながら、いろんな化学反応を生み出せることも魅力です。立場の違いにとらわれず、積極的にコミュニケーションを取れば、知見は広がり、現場のリアルな課題への理解も深まる。そこから相乗効果が生まれる実感があります。
私には、これから取り組んでいきたい大きなテーマが二つあります。
ひとつは、3年計画で掲げた最終年のテーマである「紹介体験の最適化」です。現在の仕組みでは、転職希望者がサービスに登録し、カウンセリングや検索条件の設定を経て、ようやく求人のマッチングが始まります。そこで、今よりも前の段階で求人を紹介できるようプロセス全体を見直し、リードタイムの短縮と配信者の拡大を同時に実現したいと考えています。
さらに重要なのが、マッチング精度の向上です。営業の方であれば、お客さまとの対話を通じて、顧客インサイトや企業側のニーズなど、表には出にくい情報まで把握しています。こうした深い理解を、いかにAIに再現させるか。ここに、技術者としての挑戦があると捉えています。
そして、もうひとつの大きなテーマは、「人の心に残る仕事をすること」です。技術者として、直接お客さまと関わる機会は多くありません。しかし、営業職の方たちがより良い提案や支援ができるよう、技術面から支えることで、「転職や採用に困っている誰かの力になれている」と感じています。
先日、念願だった全社アワードの舞台にファイナリストとして立つことができ、本当に嬉しかったです。けれども、それ以上に胸を打たれたのは、他のファイナリストたちの熱のこもったプレゼン、そして惜しくもファイナリストに届かなかった仲間たちを会場全体で称賛する瞬間でした。会場の一体感、湧き上がる熱量――あの光景は、きっと一生忘れません。
これからは、技術トレンドや数字を追うだけではなく、人の心に残る仕事をしていきたいと思います。
- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。
- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。
監修者:HATARACTION!編集部
"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。







 応募ガイド
応募ガイド