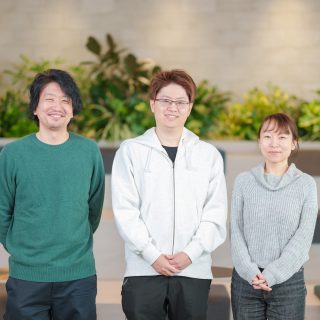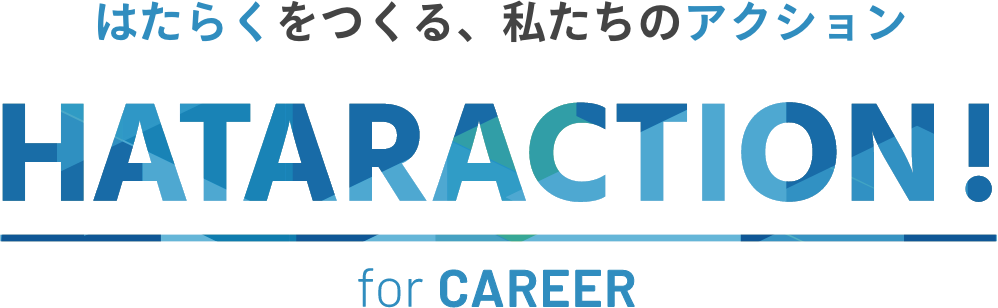社員インタビュー
2025.04.14
雇用のミスマッチを防ぎたい。そんな課題感からたどり着いた、「本質的なキャリア選択」の支援。
新卒事業部 doda新卒エージェント事業統括部 東日本新卒エージェント部 アシスタントマネジャー
林 沙紀 (はやし さき)
自身の両親がはたらく姿を見たことをきっかけに「誰かの人生に影響を与える仕事に挑戦したい」と強く望むようになり、パーソルキャリア(旧インテリジェンス)へ入社した林 沙紀さん。求人広告営業を経て、現在はパーソルキャリアとベネッセの合弁会社である「ベネッセ i-キャリア」にて、「doda新卒エージェント」のキャリアアドバイザー(CA)を担当しています。就職活動中の学生を支援しながら、アシスタントマネジャーとして組織全体の底上げに取り組む想いを聞きました。
「はたらく」を考えてまず思い浮かんだのは、両親の姿だった。
私は現在、新卒で就職活動をする学生向けのエージェント事業にて、キャリアアドバイザー(CA)を務めています。現在は自分の使命を強く感じながら仕事に取り組めている私ですが、振り返れば、就職活動を始めた当初からこの仕事を志していたわけではありません。むしろ、就職活動を通して初めて自分自身のキャリアと真剣に向き合い、「やりたいこと」を見つけていったタイプでした。
就活をする中で思い浮かんだのが、両親の姿です。私の父は料理人をしており、母は旅館ではたらいていました。ふたりが長時間労働や不規則な勤務に日々追われ、疲弊している様子が記憶に残っていたのです。その姿を見て、「はたらく環境やはたらき方は、その人の人生そのものに大きな影響を与えるものだ」と実感しました。就活の当初は漠然と「人のためになりたい」と思っていましたが、もし「はたらく」をより良くできたらもっと多くの人の人生を前向きに変えられるかもしれない――そう強く思うようになり、人や組織の「はたらく」に寄り添える人材業界の仕事に大きな意義を感じ、今の道を選びました。
パーソルキャリアを選んだのは、ソリューションが多様にある点です。「はたらく」に関連する事業を多数抱えており、ここなら企業や転職希望者のあらゆる課題を解決できるだろうという期待がありました。

「売り手市場」と言われる時代だからこそ、本質的なキャリア選択がしづらくなっていないだろうか?
入社後3年ほどは、求人広告営業の仕事に従事。その後、キャリアチャレンジ制度(※)を使い、新卒領域のサービス「doda新卒エージェント」のCAへ異動しました。背景には、求人広告営業時代に痛感した「はたらく人にもっと本質的なキャリア選択をしてほしい」という想いがあります。
※社員のキャリアデザインとその成長のために、社員自ら異動希望を出せる制度。応募タイミングは年2回。社内だけでなく、パーソルグループのさまざまなポジションに応募できる
当時私が担当していた、とある接客業の企業さま。採用施策と社員定着施策のどちらにも力を入れる一方で、離職率の高さが課題となっていました。そこで詳しく離職理由を紐解きながら考えてみた結果、企業側の情報提供や工夫だけでは解決できない、「はたらく個人側のキャリア理解や意思決定方法」にも課題があるのではないかという考えにたどり着いたのです。就職先を選ぶ上で何を大切にしたいのか。どんなはたらき方を望み、どんな未来を描きたいのか。それらを本人がしっかりと考える機会がなければ、どれだけ情報を提供してもミスマッチは起きてしまうと感じました。
だからこそ私は、キャリアの入口である新卒採用領域で、一人ひとりが「本質的なキャリア選択」をできるよう支援したいと考えるようになったのです。特に、これから初めて社会に出る学生が自分にとって納得のいくファーストキャリアを選べるようにサポートし、この先何十年も続くキャリア選択の礎を築かせてあげたい。そう考えた結果、「doda新卒エージェント」のCAが理想的な役割だと判断しました。
実際にCAとして学生と向き合う中で、早い段階から「本質的なキャリア選択」について考えてもらうことの大切さを強く実感しています。特に現在は、新卒マーケットの有効求人倍率が1.75倍を超える売り手市場。内定を得ること自体は以前よりハードルが下がっている側面があり、それゆえに深く考えずに就職先を決めてしまう学生も少なくありません。
内定獲得だけを目的とするならば、十分に企業研究や自己分析をしなくても実現は可能でしょう。しかしその未来が、「自分に合った企業に出会える」こととは必ずしも一致しません。
「条件がいいから」「なんとなく知っている有名企業だから」という理由だけで仕事の「リアル」を理解しないまま入社を決めてしまえば、入社後のミスマッチにつながります。だからこそ、自身の価値観やありたい将来像と向き合い、企業や仕事を理解した上で納得感のある選択ができるように、CAとして寄り添い、キャリアの基盤を一緒につくっていきたいです。

「doda新卒エージェント」のCAは、必ず学生を主語にする。
やりたいことが明確に定まっている方も、まだ模索の途中にある方も。一人ひとりの状況に応じて、私たちは就職活動全般の相談対応や企業求人の紹介から、採用試験対策、最終的な就職先決定まで、多面的なサポートを行っています。スキルマッチ重視の中途採用とは異なり、ポテンシャルを軸とする新卒採用は、学生一人ひとりがどのようなキャリアも描ける可能性に満ちた世界。就職活動を通して自分自身と向き合い、キャリアについて主体的に考えながら成長していく彼ら彼女らを間近で見るたび、その可能性の大きさを実感します。また、その選択が今後数十年にわたる人生の方向性を大きく左右するからこそ、私たちも大きな責任を感じながら向き合っているのです。
「doda新卒エージェント」のすべてのCAが、大切にしている姿勢があります。学生一人ひとりが自分と向き合い、納得のいくキャリア選択ができるよう、本質的な支援を行うことです。CAが徹底するのは、常に学生を主語に置いたサービス提供。提案の内容や関わり方が、本人にとって本当に意味のあるものか。その提案が、将来を見据えた選択につながるか。日々、学生の視点を持ちながら支援に向き合っています。
最近、「オワハラ」と呼ばれる行為が社会的な問題として注目されるようになりました。私たちが大事にしている「学生を起点とする支援」は、そうした事象の発生以前から一貫して大切にしてきた価値観です。この考え方は、CAだけにとどまりません。企業と向き合うリクルーティングアドバイザー(RA)も、学生に多様な選択肢を届けられるよう、常に企業への提案や求人の質にこだわり抜いています。
他の事業部では、各大学と連携しキャリア教育授業を行ったり、GPSという学生のビジネス素養を測る適性検査開発・提供したりしています。これは、キャリアのプロであるパーソルキャリアと、学びのプロであるベネッセの合弁会社だからこそできることです。就職活動を始める前の学生とも接点を持ちながら、ベストなキャリア選択につながるキャリア教育ができるのは大きな強みです。

若い組織を、マーケットの変化に負けない組織へ。私にそれを一任してもらえる面白さがある。
現在私は、アシスタントマネジャーとしてCA組織のマネジメントを担っています。新卒採用は、中途採用と比べてマーケットの変化が極めて激しい領域です。経団連の方針変更や選考時期の変動、学生の価値観の多様化などもあり、前年と同じ手法が翌年には通用しないことも珍しくありません。
また、新卒領域のCAは業界や職種を限定しないため、あらゆる業界や職種の知識と対応力が求められます。たとえば、ひとつの面談の中で、IT・メーカー・商社といった複数業界の違いや、営業・企画・エンジニアの役割やキャリアパスを整理しながら比較検討を促す、という場面も日常的に発生します。売り手市場が続く昨今、学生の選択肢が広がるからこそ、企業や職種理解・意思決定支援において求められる知識の幅や専門性がより一層高まっているのです。
このような環境下で求められているのは、属人的なスキルや経験則に依存する支援ではなく、根拠ある知識・データをもとに組織全体で再現性の高い支援力を高めていくこと。私がアシスタントマネジャーとして目下取り組んでいるのが、まさにこの組織としてのスキル標準化・底上げです。面接対策のノウハウ、業界職種ごとのキャリアパスや転職の可能性も含めた知識、労務知識まで、どのCAが対応しても一定水準の支援を提供できる状態を目指し、ナレッジの言語化・体系化・育成体制の整備を進めています。組織として質の高い支援を継続的に提供できるよう、仕組みづくりに日々取り組んでいます。
私たちは、まだ若い組織です。「doda新卒エージェント」を運営する「ベネッセi-キャリア」も立ち上げから11年ほどのため、社内でまだ整備されていない領域も少なくありません。ただその分、自分たちでサービスや組織を作っていける面白さがあります。若い組織の底上げを、どうすれば実現できるのか。アシスタントマネジャーとして、さまざまな切り口からその問いに向き合っているところです。
大変なことももちろんありますが、「やってみたい」と手を挙げれば任せてもらえる環境があるのは大きな魅力だと感じています。市場変化のスピードが速いからこそ、現場の声や肌感覚をもとに戦略や仕組みをつくっていくことが不可欠であり、現場にいる私たちが主導するからこそ出せる価値もたくさんある。 実際に私も、日々メンバーの声を直接聞きながら、仕組みや施策に落とし込むことを大切にしています。よりよいキャリアと就活に、もう一歩踏み込めるCAのあり方を、自分たちでつくっていきたいです。
- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。
- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。
監修者:HATARACTION!編集部
"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。







 応募ガイド
応募ガイド