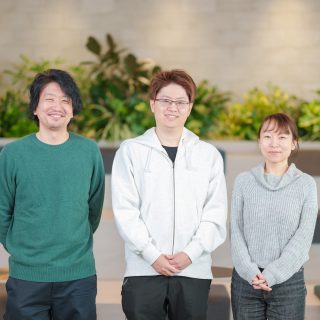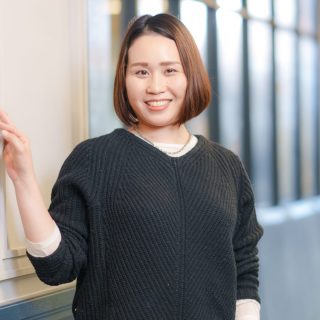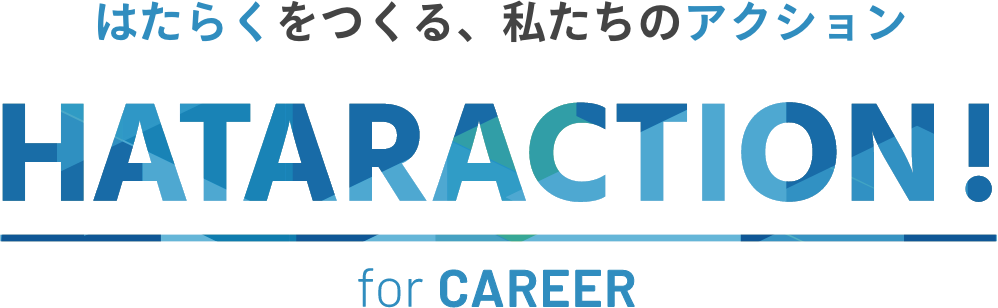社員インタビュー
2024.02.06
社内起業のススメ。本業に軸足を置きつつ、夢をかなえる「メリットしかない」はたらき方
新規サービス開発本部 新規サービス開発統括部 サービスシード部 エンジニアパスグループ マネジャー
中矢 恭史
若手エンジニアの現場育成を支援するサービス「エンジニアパス」。パーソルキャリアの新規事業創出プログラムを通じて誕生したプロジェクトです。サービスに込めた思いや、社内起業のメリットについて、サービスオーナーの中矢 恭史にインタビューしました。
自ら意思決定できる環境を求め、企画職でパーソルキャリアへ
大学では、教育学を専攻していました。教育の仕組みづくりに関心があり、教材をつくる仕事がしたいと考えて、新卒で教育系の出版社に就職したんです。社会人になって初めて担当したのがオカルトやアニメの雑誌の営業の仕事でした。教育とはかけ離れた分野で、すぐに編集の仕事に移ることも難しそうだったので、転職を考えました。
2社目に経験したのが、Web制作会社です。当時盛り上がっていたIT業界で、企画の仕事をしたいと思ったからです。WebディレクターとしてはたらきながらIT・Webに関する知識を学びましたが、望んでいた企画の仕事にはなかなか就けなかったこともあり、再び転職活動を始めました。
新しいシステム・プロダクトやサービスを持っている事業会社なら、若い自分であってもある程度の業務の意思決定を任せてもらえるのではないかと思い、業界にはこだわらずに仕事を探していたときに出会ったのがパーソルキャリアです。面接で会った方は、事業の概要や業務内容について、私が質問をする前にしっかり話してくれました。その時、パーソルキャリアではたらく人はみんな「思い」を持って仕事をしていることが伝わってきましたし、Webディレクションのスキルも活かせそうだと感じて、入社を決めたんです。
入社後は、doda Recruiters(現:dodaダイレクト)で、Webディレクションの仕事をしました。入社前の希望通り、自分で意思決定をする範囲が広がり、常に、「君はどうしたいの?」と問われましたね。この社風に慣れるまで、半年ほどかかりましたね。その後、PM(プロダクトマネージャー)として、戦略立案やチームの体制構築も担当するようになりました。

新規事業創出プログラムに毎年応募。エンジニアパスのアイデアが生まれる
入社以来、毎年パーソルグループの新規事業創出プログラム「Drit」に応募し続けていました。本来の業務でしっかりと責任を果たし結果を出すことが前提ですが、パーソルキャリアには、個人が「やりたい」と手を挙げたことについて、真剣に話を聞いてくれる文化があります。社員がやりたいことをビジネス化する仕組みも整ってきているんです。
私は、新しいアイデアを提案することが、学生時代から好きでした。星野 源さんが、「行ったことのない場所に行かないと耐えられない」という意味のことをたびたび発言されているのですが、私もそんな感じで。やったことがない領域に挑戦し続けないと、生きていけないんです(笑)。中には最終審査まで残った企画もあったのですが、事業化するところまではたどり着けませんでした。
日々PMとして仕事をする中で、IT業界における人材確保の厳しさを目の当たりにしてきました。とくに中小企業では、営業のメンバーがお客さまと協力して発信方法を工夫しても、思うように転職希望者が集まらないことが多いです。「採用が難しいなら、育成によって顧客企業の課題を解決できるのではないか」と考えたことが出発点となり、「現場で、OJTを通じてエンジニアを育成する」というエンジニアパスのアイデアが生まれました。
エンジニアパスは、Drit1回目の応募で最終選考まで残ったのですが、実は落選してしまったんです。結果を知らされて落ち込みましたし、悔しかったことを今でも覚えています。
Dritでは、パーソルグループの経営陣が審査にあたります。企画の意義やオペレーションについてどれだけ説明を重ねても、納得してもらうことができませんでした。「中矢くんがそのアイデアを事業化したいのはわかったけれど、どうして会社が出資をしなければならないの?」などと問われ、なぜ伝わらないんだろう、と正直2年くらいは悩み続けましたね(笑)。

視座が高まったことで、事業化への道がパっと開かれた
そんな時、ブレイクスルーのきっかけになる出来事がありました。社内のメンターから、「中矢は、ずっと経営者の関心の外にあることについてしゃべっているんだよ」と指摘されたんです。私は経営陣に対し、エンジニアパスが育成課題を解決する仕組みや実務について話していたのですが、投資判断をする立場の人たちが知りたいのは、市場のニーズやマネタイズの仕組みなんだ、と気づきました。新規事業界隈には、「右手にロマン、左手にソロバン」という言葉がありますが、まさにその通りで。新規事業には夢や思いが欠かせませんが、同時に収益が上がらなければ、事業は持続できないんです。
視点が切り替わったことで、プレゼンでも「伝わっている」という手ごたえを得られるようになりました。Dritから、パーソルキャリア独自の社内起業制度「OWNERS」に移管して臨んだ審査で、事業化が決まったんです。
実証実験を進める過程で、とあるIT企業の方にオンラインでインタビューをする機会がありました。会話の中で、エンジニアパスの活用により育成課題を克服する道すじが見えてきたのです。インタビューが終わった瞬間、チームの仲間と、「エンジニアパスが支援できるお客さまが、本当にいたね」と言い合って泣きながら喜んだのを今でも覚えています。自分の子どもが生まれた時と同じくらいうれしかったです。
事業化が決まり現在の部署に異動するまで、本業と新規事業の二足のわらじ状態での勤務スタイルがスタートしました。というと、果てしなく大変そうに思われますが、家庭との両立もかなっています。週3日は18時ごろに退社して、保育園へのお迎えから子どもの食事、寝かしつけまで1人で担当していますよ。その代わり、週2日は育児を妻にお願いして目一杯仕事をし、メリハリをつけています。家庭を持ちながら新規事業に挑戦できるのは、社内起業の大きなメリットですね。

転職活動をやめ、パーソルキャリアに残ることを決断した理由
社内起業には、リスクがないんです。私自身がそうだったように、チャレンジを通じて本業に活かせるスキルが身につきますし、事業が成長すれば、将来は事業部長になれるかもしれない(笑)。もちろん時間的には忙しくなりますが、リスクをとらず、自分のキャリアパスや自分がより輝ける場所をつくっていけるので、個人的には「メリットしかない」と感じています。
パーソルキャリアで新規事業をはじめるというのは、なかなかイメージが沸かないかもしれませんが、「人材業界に興味のない人こそ、ぜひおいで!」と伝えたいですね。人材紹介サービスというビジネスモデル自体は、決して新しいものではありません。ただ、「人」という経営資源を扱っているがゆえに、市場のトレンドを見据え、あらゆる業種・職種に関わる事業開発を手がけることができるのです。社会貢献と、持続性のあるビジネスという両方の条件を満たす事業を立ち上げたい方には、ぴったりの環境だと思いますよ。
実は、最初にエンジニアパスのアイデアが落選したころ、「転職しようかな……」と考えたことがあって。実際に複数の企業の選考を受けたのですが、書類選考はほぼ100%通過できましたし、好待遇で最終面接まで進んだ企業も数社ほどありました。パーソルキャリアでの業務を通じて、どこでも通用するスキルが身についていることを実感しましたね。自信が持てたことで、ここに留まることにもなりました。会社員を続けながら起業に挑戦できる環境にいられることこそ、なかなかない環境だと思って。
パーソルキャリアは、「会社に育ててもらおう」と受け身ではたらいていたらスキルは身につかない環境だと思いますが、主体的に「これがやりたいです」と手を挙げて挑戦できる方であれば、得られるものはたくさんある会社だと思います。
生成AIが台頭し、これまで存在した仕事がなくなったり、新たな職種が生まれたりして労働市場が様変わりする現代は、まさに時代の変わり目です。今、皆さんは産業革命の真っただ中にいると言えるかもしれません。そんな転換期に人材業界ではたらくことは、きっとおもしろい経験になるのではないでしょうか。
- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。
- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。
監修者:HATARACTION!編集部
"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。







 応募ガイド
応募ガイド