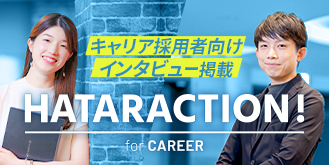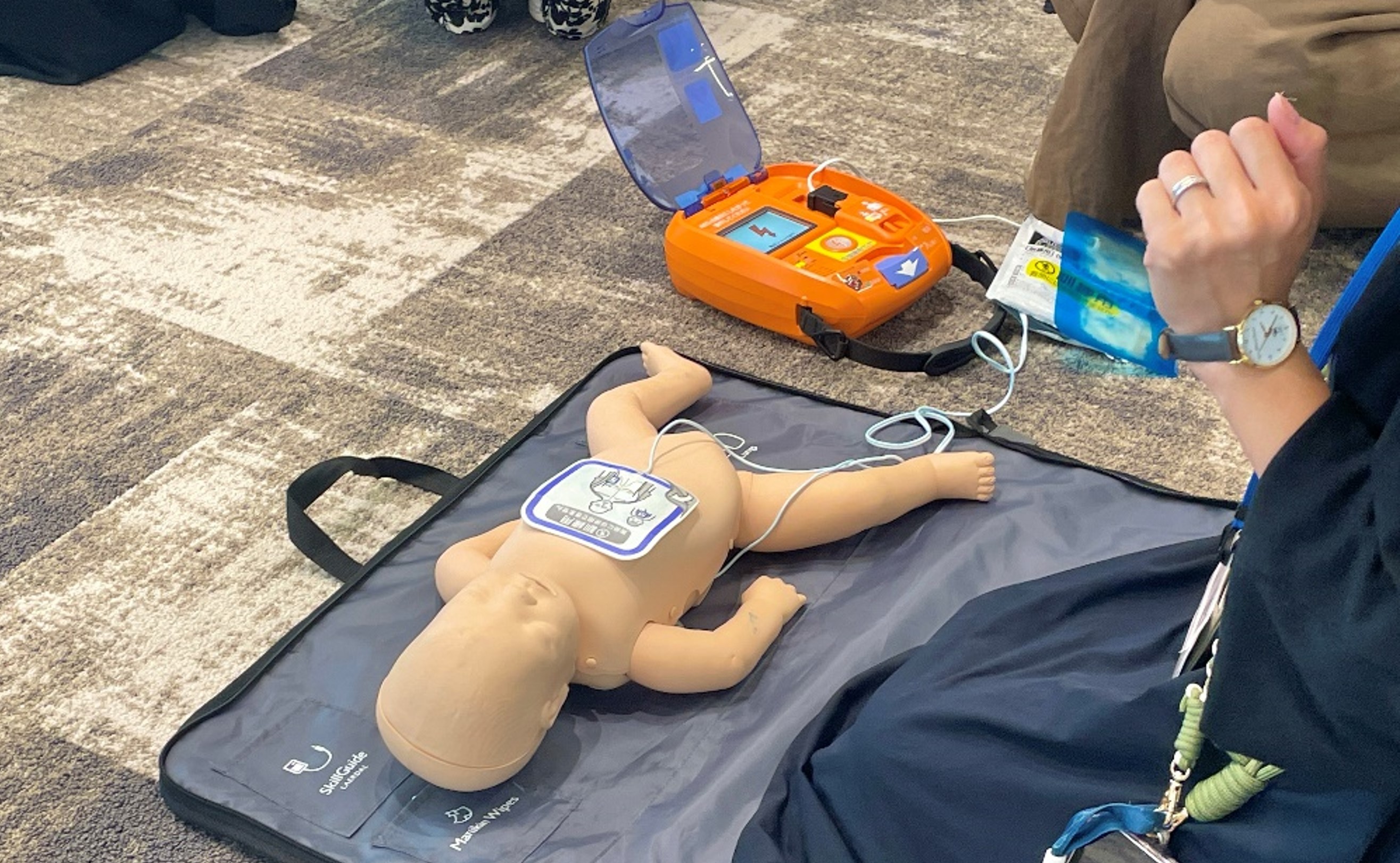子どもの病気やけがなどで会社を休む必要があるときに利用できる、子の看護等休暇制度。しかし看護等休暇が有給になるか無給になるかは企業によって異なる。この記事では、子の看護等休暇とは何か、そして有給で育児のための休暇を取得できるパーソルキャリアの制度について解説する。あわせて、女性活躍推進のためのパーソルキャリアの取り組みも紹介。
子の看護等休暇とは
子の看護等休暇とは「育児・介護休業法」によって定められており、厚生労働省では以下のように定義している。
子の看護等休暇とは、①負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、②子の疾病の予防を図るために必要な世話(則第32条)、③学校の休業等に伴う子の世話(則第 33 条)、又は④子の入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典への参加(則第 33 条の2)を行う労働者に対し与えられる休暇
| 対象者 | 小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者 |
| 取得できる休暇日数(年度) | 1年度のうち5日(当該子が2人以上の場合は10日) 1日単位、又は半日単位・時間単位での取得が可能 |
| 年次有給休暇との扱いの差 | 年次有給休暇は目的を限定しないが、子の看護等休暇は子どもの看護等にのみ目的が限定される |
| 利用できるシーン | 子どもの病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式 |
子の看護等休暇は、子どもが小学校3年生修了までであれば取得が可能。当該子が2人以上の場合、取得できる休暇日数は10日までとされている。
子の看護等休暇は有給?無給?
子の看護等休暇を取得する際、給与が支給されるかどうかは法律で定められていない。有給か、無給かは企業(事業主)の判断となる。
厚生労働省の「令和3年度雇用均等基本調査」によると、本制度を取得した場合の賃金の取扱いについては「無給」が 65.1%、「有給」が 27.5%、「一部有給」が 7.4%となっている。
パーソルキャリアの子育て支援制度「次世代育成休暇」は有給
パーソルキャリアには無給の子の看護等休暇に加え、有給で取得できる「次世代育成休暇」が設けられている。
「次世代育成休暇」は、時短社員の子どもが小学校にあがるまでの間、年間最大12日間休暇を取得できる制度だ。子の看護等休暇との違いは下記のとおり。
| 次世代育成休暇 | 子の看護等休暇 | |
| 対象者 | 小学校就学前の子どもを養育する、勤続1年以上の時短社員※ | 小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者 |
| 取得できる休暇日数(年度) | 付与月・労働日数に応じて最大12日 | 5日(当該子が2人以上の場合は10日) |
| 有給・無給 | 有給 | 無給 |
| 利用可能シーン | 子どもの看護のほか、子どもの行事への参加など幅広いシーンで利用可能 | 子どもの病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式 |
※所定労働時間の短縮・所定外労働の制限をしている社員のこと
子育て中は、子どもの病気だけでなく行事などでも会社を休むことがあり、有給休暇が不足してしまうことも。しかしパーソルキャリアでは、年次有給休暇とは別に「次世代育成休暇」を利用できる。このため、子どもの病気や行事で年次有給休暇を使い切ってしまう社員は少ない。
「次世代育成休暇」だけではない!パーソルキャリアの女性活躍推進の取り組み
パーソルキャリアには、「次世代育成休暇」のほかにもさまざまな女性活躍推進の取り組みがある。例えば以下のような制度だ。
| 制度名 | 内容 |
| はたらき方支援制度 | リモートワーク フレックスタイム制度 家事代行サービス、育児代行サービス(会社負担の補助金あり) |
| キャリア支援制度 | i-design ジョブトライアル制度 キャリアチャレンジ制度 |
| 女性管理職向け キャリア支援制度 | スポンサーシッププログラム アンコンシャスバイアス研修 自分らしいリーダーシップ発見ワークショップ 女性管理職×女性メンバーの座談会 |
| その他 | 健康とライフキャリアの両立リテラシー向上施策(e-Learning) 制限のあるはたらき方理解研修 |
パーソルキャリアにおける社員のはたらき方は自由で、多様性を大事にしている。またそれを応援する風土も根付いており、同僚や上司も個人のはたらき方を尊重している。
実際パーソルキャリアの女性社員で、他社を第1子妊娠のために退職したあと、パーソルキャリアへ転職し、第2子を出産後に復職している実例もある。子育て期間でブランクがあってもキャリアを応援してくれる会社の風土は非常にはたらきやすいという感想を持つ女性社員が多い。
まとめ
パーソルキャリアでは「次世代育成休暇」のほかにも、女性活躍推進制度を実施し、多様なはたらき方やキャリア形成のための支援など、さまざまな状況に適した制度を拡充中だ。このような支援制度を利用し、社員それぞれが活き活きと、キャリアオーナーシップを育める環境をこれからも作っていく。
編集:パーソルキャリア広報部