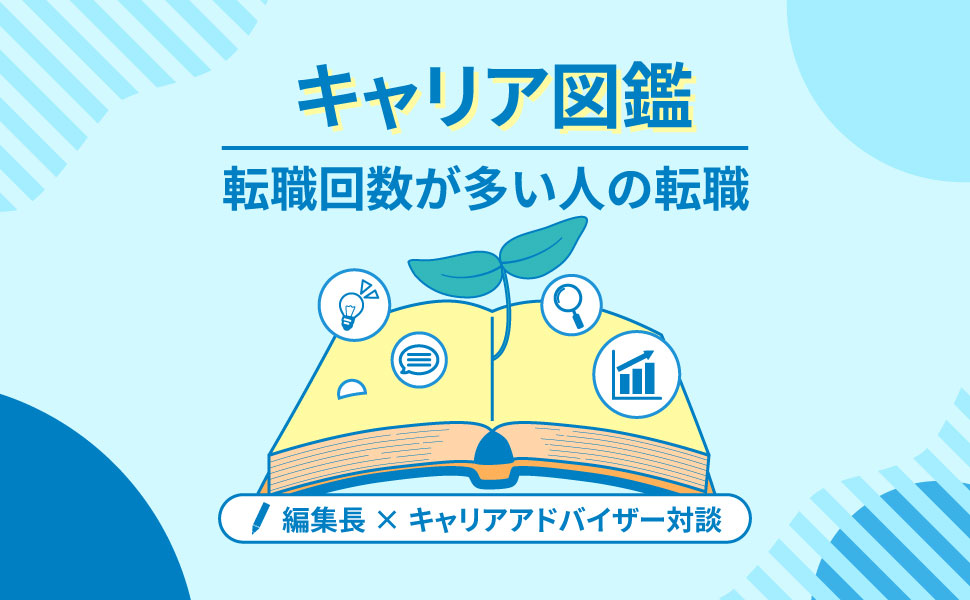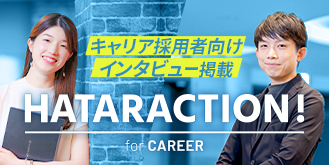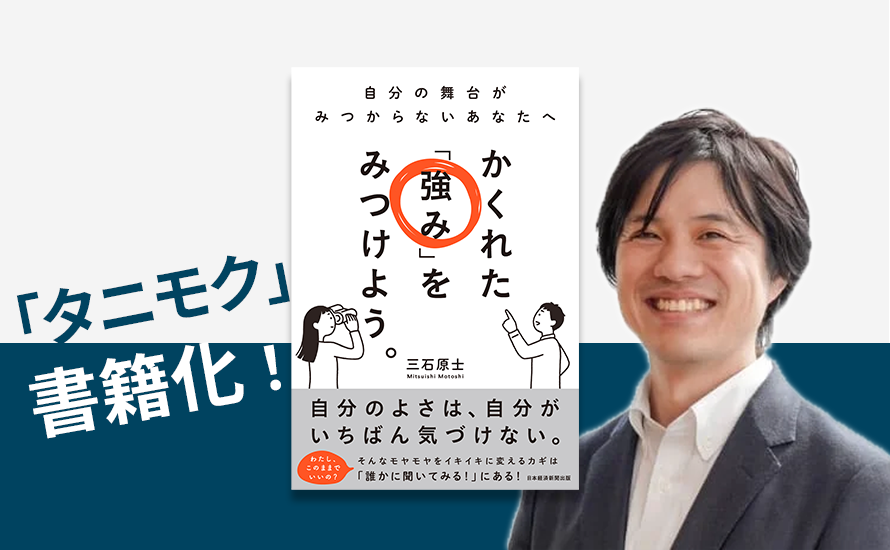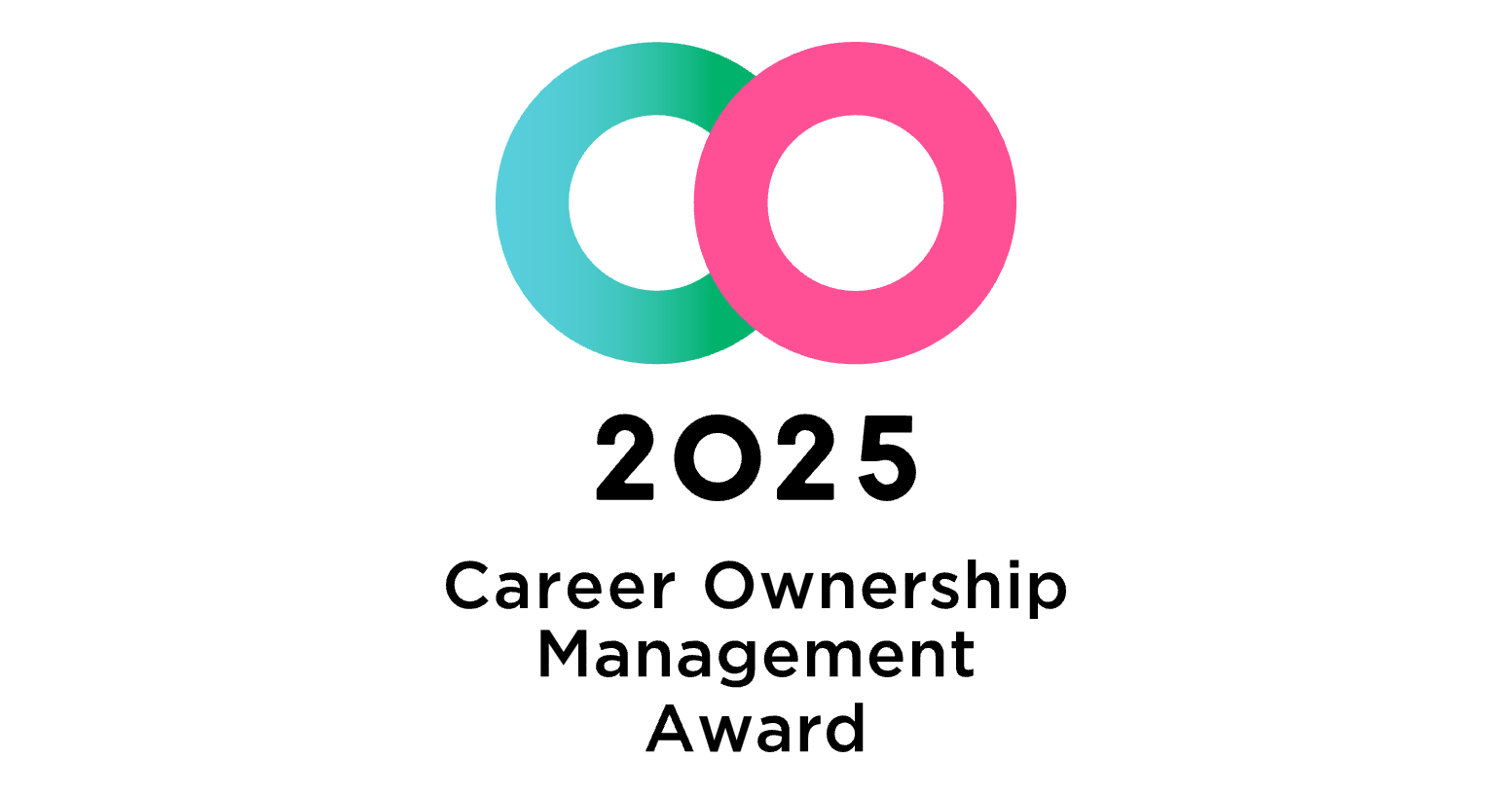皆さんは、「キャリアオーナーシップ」と聞いて何を想像しますか?「キャリア志向な人」「意識が高い人」、または「成長し続けること」「キャリアアップしていくこと」…… そんなことを思い浮かべるのではないでしょうか。「キャリアオーナーシップを育む社会の創造」を目指すパーソルキャリアは、自分の可能性を信じ、自分の意思でキャリア、そして人生を選択することが、「キャリアオーナーシップ」だと考えています。「キャリア図鑑」では、当社のサービスを通じ、自らが望む「はたらく」をかなえた人たちの事例も交えながら、「キャリアオーナーシップ」発揮のヒントを探ります。
今回は、doda編集長の桜井貴史が、dodaキャリアアドバイザーの小菅裕子に話を聞きました。
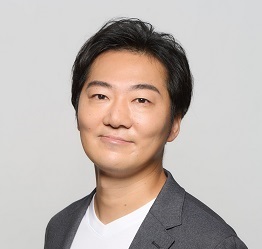

転職回数が多くとも転職できる。“回数”の多さだけで不利にはならない
doda編集長 桜井(以下、桜井):前回のテーマは「50代の転職」でしたが、今回は打って変わって「転職回数」に焦点を当てたいと思います。
転職が以前より身近な時代になってきましたが、転職回数が多いとキャリアを築いていく上で不利になるのではないか、と不安に思う人は少なくないですよね。転職回数という観点で、現場で転職をサポートしている小菅さんは何か変化を感じますか?
dodaキャリアアドバイザー 小菅(以下、小菅):5回や8回、10回以上など、転職を重ねた人からの相談は確実に増えています。また、業種や職種にもよりますが、転職のハードルも下がったように感じています。
転職回数に関して一定基準を設け、シビアな目で吟味しているケースはもちろんあります。しかし、中途採用が活発化していることもあり、定着性という観点では見られていますが、回数自体は昔ほど厳しくは見られていませんね。
桜井:今、小菅さんが「定着性」と言いましたが、転職を重ねていると、またすぐに辞めてしまうのではないか。そう思われてしまう恐れは確かにありますよね。しかし年齢を重ねた分、転職回数が多くなっている人もいるでしょうし、短期離職を繰り返してきたわけではない人もいるでしょう。一概に回数の多さだけでは不利にならないということですね。
小菅:おっしゃるとおりです。しかしながら、条件はどうしても厳しくなってしまうのが現状です。
桜井:ではここからは、小菅さんに転職事例を紹介してもらいましょう。
7回目の転職:1つの業界で積み重ねてきた経験と、培ったスキルを武器に転職
小菅:まず1つ目は、やりたいことができる企業に入社したものの、コスト削減によりそれがかなわなくなり7回目の転職を決めたケースです。
1つの業界に長く身を置き、Webディレクターやマーケティング、新規サービスの立ち上げといった職種を経験したことを強みに転職活動を行いました。結果、異業種参入を試みていた企業に、業界経験と新規事業立ち上げ実績が評価され内定を獲得。年収もアップしました。

桜井:特定の業界に特化した専門的な経験やノウハウである「ドメイン知識」と、職種の経験・スキルを掛け算で持っていると強いですよね。また、転職回数が多くても1つの業界での長い経験は、キャリアの一貫性を示せます。
小菅:おっしゃるとおり業界経験を有していれば、転職回数だけで評価が下がることはありません。経験、スキルが十分にあるなら、6回、7回、8回と転職していても採用ニーズはどこかにあります。
桜井:転職回数が多いからと悲観的になりすぎないようにしたほうがよいですよね。自らのキャリアに主体性を持って取り組む意識と行動である「キャリアオーナーシップ」を発揮し、納得感のある転職をかなえるためにも、これまでの経験やスキルの棚卸しをていねいに行うことが大事ですね。
6回目の転職:条件にとらわれすぎず、自分の経験やスキルが求められている企業に転職
小菅: 2つ目は、家族を支えていくために6回目の転職を決意。年収アップ、福利厚生の充実、はたらき方の自由度などを条件に、大手企業へ転職を望んでいたケースです。
桜井:転職先として人気の大手企業にはたくさんの応募が集まりますから、企業にとって転職回数が多いことは気になるでしょうね。
小菅:はい、選考の土俵に乗りづらいのが実情だと思います。一方で本ケースでは、少人数の企業でさまざまな経験を積んできたことや、何でも自分で調べてやってみるという精神が、規模の小さな企業では高く評価されました。さらに、条件も一定程度かなったことから、最終的にはベンチャー企業に転職を決めました。
桜井:条件面を改め、自身の経験やスキル、志向性がマッチする場所を見つけられたことが、転職成功に結び付いたといえますね。自分が一番評価されるのはどこなのか。どこなら自分は輝けるのか。それを見極めることはとても重要です。見極めに苦労している場合はぜひ、小菅さんのような第三者からアドバイスをもらってみてもよいかもしれません。新たな発見があると思います。

7回目の転職:落ち続けても前向きに。応募数を増やし内定を獲得
小菅:最後は、はたらく環境が合わないからと数年ごとに転職を繰り返しており、今回も自分に合う職場を求めて7回目の転職を決めたケースです。
桜井:短期スパンでの転職で、定着性が問われてしまうケースですね。
小菅:はい。しかしながら、最終的には納得感を持って転職を決めました。成功要因の1つは、ポジティブマインドだと思います。落ち続けても前向きに。気になる企業にはどんどん応募する。企業との巡り合わせはご縁ですから、活動量は増やさざるを得ません。また、短期離職の背景も誠意を持って説明しました。
桜井:前向きな姿勢、素晴らしいですね。まだ日本では、転職回数の多さがマイナスに働いてしまう局面はありますので、その点を留意の上、転職活動は進めていただくとよいと思います。
doda編集長の「これがキャリアオーナーシップの種」
桜井:ここまで小菅さんに3つの事例を紹介してもらいました。小菅さんは「転職回数が多い人の転職」というテーマで、「キャリアオーナーシップ」を発揮するために重要なポイントは何だと思いますか?
小菅:わたしは、過去の転職を振り返ること、応募数を増やすこと、内定を辞退するという選択肢を持つことが大切だと思います。
桜井:小菅さんが紹介してくれた事例からも分かるように、転職回数や回数が増えること自体が問題ではないのですが、過去の転職を振り返ることは、「キャリアオーナーシップ」を発揮する上でとても重要ですね。
① 過去の転職を振り返る
過去の転職を振り返ることで自身の「はたらく」の価値観が明確になり、今後のキャリアの選択のヒントが得られるかもしれません。どうしても譲れない価値観を満たし、かつ自分にとってプラスになるほかの要素もあるキャリアの決断ができるとよいのではないでしょうか。
② オファーを断る勇気を持つ
「転職を重ねている自分が採用されるわけがない」「転職回数が多いと絶対不利になる」そういった心理が強く働いていると、オファーがもらえた企業に決めてしまうことが往々にしてあります。しかしどんなに条件が良くても、自分の「はたらく」の価値観に合致しないオファーに飛びついてしまうと短期離職しかねません。逆に、条件が多少悪くても、「はたらく」の価値観に合致していれば長く勤められるかもしれません。一つひとつが貴重なオファーですから、誤ったキャリアの選択をしないよう、あらかじめ転職先を選ぶ際に譲れない条件をしっかり定めておくことが大事だと思います。
◆関連記事
50代転職-年齢を重ねるごとに厳しくなるといわれるが、成功への道は?-
※掲載している内容・社員の所属は取材当時のものです。
編集:パーソルキャリア広報部